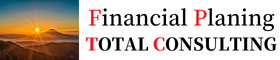学生納付特例制度の利用は年金が満額ではない。年金の満額方法。
20歳になると国民年金に加入して保険料を納付することになりますが、その年齢時に大学生の人は収入がアルバイトのみであるため納付が厳しく、学生納付特例制度を利用した人が多いのではないでしょうか。
実は、その学生納付特例制度を利用することで、将来的に受け取ることができる年金額は減ってしまうので注意が必要です。
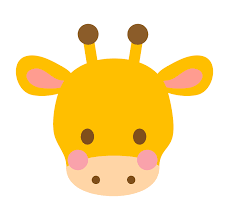
学生納付特例制度を利用して、年金受給の確保をした方も多いのではないでしょうか。
学生納付特例制度は、年金の受給権を確保するのに有効な制度です。ただ年金額を満額にするわけではない為、注意が必要です。

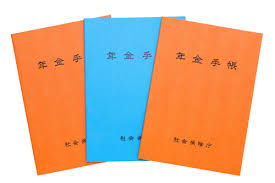
学生納付特例制度とは、学生が申請することにより、年金の納付が猶予される制度です。この制度は、将来の年金受給権を確保するだけではなく、障害や事故を負った時の障害基礎年金基金を受給することが出来る為、学生で年金の支払いが出来ない場合には、必ず入る方が良いと思います。
特に、20歳になってから就職するまでの間が長く心配な人は追納によって将来的に受け取ることができる年金額を増やすことも検討しましょう。
この記事は、こんな人におすすめです。
- 学生時に学生納付特例制度を利用していた人
- 未納の年金期間が将来どのように影響するか気になる人
- 年金の追納を検討している人
よく聞く国民年金の「満額」とは国民年金の「満額」とは、具体的に何円なのかご存じでしょうか。
この金額は年度によって物価に合わせて変動しますが、2022年度は年間の支給額で777,792円(64,816円 ×12ヶ月)です。
これは、20歳〜60歳の40年間に国民年金保険料を毎月納めた場合に、65歳以降に支給される年間の支給額であり、俗に「満額」と呼ばれています。
今回のポイントです。
- 学生特例納付制度は、年金を満額に出来るものではない、将来の年金受給権を得るためのもので、満額にするには、学生納付特例制度終了後の3年以内に納付すると増額されずに納付できます。
です。
学生納付特例制度の利用によって「満額」から減ってしまう金額
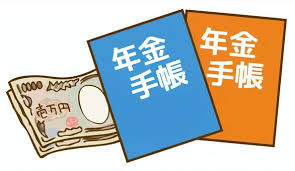
先ほど少し説明しましたが、国民年金保険料を納めることができる最大の期間は20歳〜60歳の40年間(480ヶ月)です。
ここから学生納付特例制度の利用によって国民年金保険料を納めていない期間を引いた期間に相当する金額を、65歳以降に年金として支給されることになります。
注意点として、学生納付特例制度は国民年金保険料の納付を完全に免除する制度ではないことを理解しておきましょう。
学生納付特例制度は、65歳以降に年金が支給されるための条件である「支払いの実績がある期間」のみを満たす制度です。
その期間には国民年金保険料の納付が無いため、将来受け取ることができる年金額には反映されない期間となります。この期間のことは「カラ期間」と呼ばれます。
それでは、学生納付特例制度による「カラ期間」によって、具体的にどれくらい将来受け取ることができる年金額が減ってしまうのか計算してみます。
例として、22歳で大学を卒業後にすぐ就職して厚生年金に加入した人の場合を考えますと、学生納付特例制度による「カラ期間」は2年間、つまり24ヶ月です。
この期間が上記の「満額」に占める割合を計算しますと、777,792円× (24ヶ月 / 480ヶ月) = 約38,890円となります。
この金額が、65歳以降に支給される年金の満額から毎年引かれてしまうことになります。
将来的な年金を「満額」へ近づける方法

先ほど算出した金額はそれほど大きくありませんが、人によっては将来的に受け取ることができる年金を「満額」に近づけたいと感じるでしょう。
そのための方法としては、学生納付特例制度の終了後に後から国民年金保険料の納付ができる追納がおすすめです。
しかし、追納には下記の注意点があります。
- 追納が可能な期間は学生納付特例制度終了後の10年以内です。
- 学生納付特例制度終了後の3年度目以降は、追納額は当時の年金保険料から増額されます。
上記を踏まえますと、追納は学生から社会人になった早い段階で検討するべきだと言えます。
まとめ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。この記事では、学生納付特例制度を利用することで、将来的に受け取ることができる年金額がどれほど減ってしまうか具体例を出して説明しました。
そして、将来的に受け取ることができる年金を「満額」に近づけたい場合の手段として追納と、その注意点を紹介しました。
もし追納される場合は、早い段階ならお得ですので事前に知識だけでも身につけていれば後々役立つはずです。
今回のポイントです。
- 学生特例納付制度は、年金を満額に出来るものではない、将来の年金受給権を得るためのもので、満額にするには、学生納付特例制度終了後の3年以内に納付すると増額されずに納付できます。
お金の話に関して、メルマガでも発信しています。

にほんブログ村
ファイナンシャルプランニングランキング