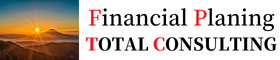不動産売買取引のトラブル解決手段
不動産売買取引では多額のお金が動くので慎重な取引が必要となります。しかし、残念ながらトラブルが絶えず紛争が多数発生しているのが現状です。不動産のプロである業者と一般消費者では大きな情報格差があります。消費者側はトラブルの際に何を頼ればよいのか解りません。今回は消費者側のトラブル解決手段についてお話し致します。
トラブル防止の為に

重要事項説明で内容をよく理解してから契約書に進みます。不明点は不動産業者に遠慮せず質問しましょう。一連の契約手続きでトラブルになりやすい項目を列挙します。
*ローン特約、手付解除、違約解除-→適用期間に注意
*契約不適合、心理的瑕疵―→新築・中古問わず。心理的瑕疵は物件外部にも注意。
*接道、法令制限、周辺の建築計画・都市計画-→将来の住まい状況に関わります。
*契約の覚書-→契約時から引渡し時迄の間に変更が生じた場合に取り交わす書面です。
知っておくとよい法律
不動産売買取引は様々な法律が関係します。民法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法等多数。その中でも一般消費者が知っておくとよいと思われる法律をご紹介します。
*宅地建物取引業法34条(媒介契約)・35条(重要事項説明)・37条(契約書)
*民法1条2項(信義誠実の原則)・415条(債務不履行)・
709条(不法行為による損害賠償責任)
*消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する契約の無効)
2つのトラブル解決ルート

相談機関への相談による解決と、紛争機関への訴えによる解決の2つがあります。相談機関で解決しない場合、次に紛争機関へと移る場合もあります。
相談機関を利用したトラブル解決
*住まいるダイヤル
国土交通省指定の住宅専門の相談窓口です。建築士等の専門家が相談に応じてくれます。
*弁護士会
いきなり訴訟はハードルが高いので、まずは弁護士に相談したい。しかしどこに連絡すればよいのか判らない。弁護士会から不動産に精通した弁護士の紹介を受けて相談してみましょう。
*法テラス(日本司法支援センター)
国が設立した無料の弁護士相談所。但し、利用には収入や保有資産の要件があります。
*不動産流通推進センター
不動産取引に関する相談を専門の相談員が電話で応じてくれます。
*国民生活センター
消費生活全般に関する苦情や問い合わせを相談員が受け付ける独立行政法人です。
*消費者ホットライン
消費者庁による消費生活相談窓口です。
*宅地建物取引業の免許権者(国土交通省。都道府県知事)
不動産業者には営業免許があり、管轄は国土交通省または都道府県知事です。 免許の付与・取消、指導・勧告・業務停止などの権限があり業界の健全な運営を監視します。
(紛争機関を利用したトラブル解決)
*ADR(裁判外紛争解決制度)
裁判以外の紛争解決制度。専門家を介した当事者間の任意の話し合いです。裁判よりも安い費用で、早く解決できる可能性があります。但し、ADRに相手方が応じるかどうかも任意です。
例:日本不動産仲裁機構、不動産専門のADR機関。

申立て手数料 11000円(相手方がADRに応じない場合は半額返金)
話合い期日手数料 11000円(相手方と折半)
解決金手数料 最終解決金額に対して所定の金額(相手方と折半)
相手方がADRによる話合いに応じない場合は終了となる。
*訴訟
裁判所による法的解決。ADRの様な任意による話合いではなく強制力があります。
*宅地建物取引業保証協会
業界団体。多くの不動産業者はこの団体に属しており、その名の通り保証機関があります。不動産取引における消費者からの苦情・相談を受け付け、トラブル解決に向けて相談員を介し話合いが行われます。不動産業者の責任が認証された場合は保証協会が消費者に損害金を支払います(限度金額あり)。消費者側の申し出に関わる費用は無料で、相手方はこの話合いを原則拒否出来ません。
その他補足
*宅地建物取引士賠償責任保険
不動産業者が任意に加入する民間保険です。宅地建物取引士が取引事故を起こした(重要事項説明義務違反等)場合に保険金が支払われます。消費者から保険会社への申し出は不可であり、保険契約者である不動産業者から保険会社への申し出(事故報告)となりす。
お金の話に関して、メルマガでも発信しています。

にほんブログ村
ファイナンシャルプランニングランキング